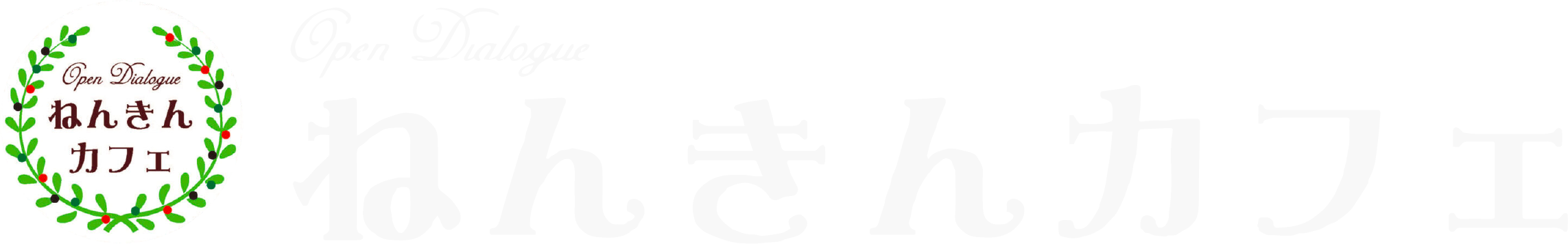クルーズ船を含む、国内のコロナ感染死が1000人に達したといいます。「医療」「情報」ともに今とは比較にならなかったであろう、百年前の「スペイン風邪」では、世界で5億人が感染し、日本でも38万を超える人が命を落としました。1920年に、与謝野晶子が発表した「死の恐怖」と題する随筆には、こう記されています。「 死に対する人間の弱さが今更のごとく思われます。」「人間の威張り得るのは「生」の世界においてだけの事です。」と。
十人以上いたらしい晶子の子のうち、ひとりの感染がきっかけで家庭内感染がひろがったという彼女はこうも記しています。「 自分一個のためというよりは、子どもたちの扶養のために余計に生の欲望が深まっていることを実感している」と。自分が死を恐れるのは、自分の死によって引き起こされるであろう子どもの不幸を、何としても回避したいからだというわけです。この一文を目にした時、とっさに、わたしの目の前にはある映像が浮かびました。
もう、四半世紀も前のことです。在職中にうつを患い当時、病院にいたわたしは、生きている1分1秒が苦痛でならず、階下のアスファルトをみつめては、このまま飛び降りたら楽になれると、ぼんやりとした頭で考えていました。そんなとき、もうひとりのわたしが現れて微かな声で叫ぶのです。「おまえが死んだら、この世におまえの他に母を持たない、幼い娘たちはどうなるのか?」と。微かな声はしだいに大きくなり、今もわたしはこうして生きていて、あのときほどは娘たちから必要とされなくなりました。
それでも、わたしが人生をギブアップしないのは、しぶとく生きることが次の世代の肥やしになると信じて疑わないからかもしれません。なので、次に心が折れそうな時は、これを頼りにサバイバルしようと思います。好むと好まざるとに関わらず、コロナによって「命の選別」の問題が顕在化しつつある時代に、この先やがて高齢期を迎えるわたしが、いかに生き、いかにその生をまっとうしたかが、娘たちを含む次の世代の励ましになるような、できることならそんな生き方がしたいから。