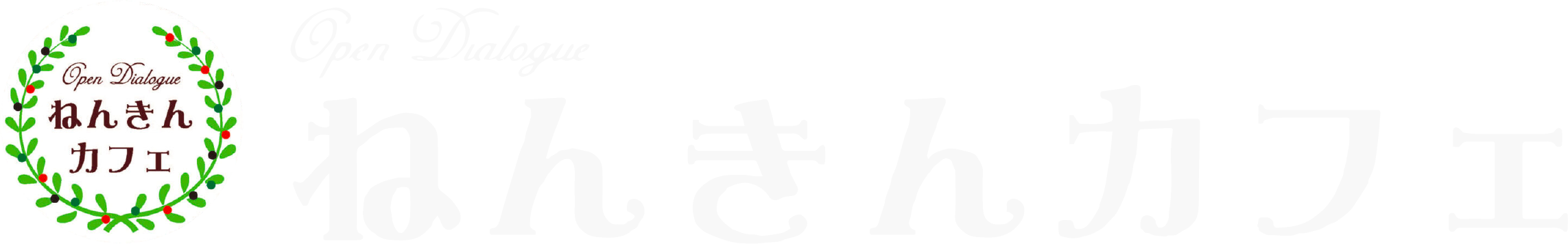「自分が死んだら、インド洋に流してくれ」これが父の遺言でした。「それが無理なら瀬戸内海でもいいから」とも。なぜ、インド洋なのかは、聞きそびれてしまっていまだによくわかりませんが、昨日書いたピースボートで、父がその美しさに魅了されたからかもしれません。父は、この世の生を終えてなお、海流に乗って世界を巡りたかったのだと、わたしがはっきり気付いたのは、インド洋に浮かぶセイシェル諸島のラ・ディーグ島沖で、遺骨の一部の散骨を滞りなく終えた安堵の中でした。
セイシェルは遠いです。でも、父亡き後のわたしは、娘の赴任先だったインドにいったん戻っていたので、けっこう身近だったのです。もしも、旅行社が企画するような散骨ツアーに参加するしか選択肢がなかったとしたら、とても手が出なかったでしょうが、幸い積極的な娘の協力が得られ、彼女が島のビーチの若者に交渉して船を出してもらえることになったからこそ実現できたことでした。しかし、そもそも、父はなぜ海洋散骨を望んだのか。
住職を継がなかったとはいえ、お寺に生まれた長男なので、仮に意思表示がなかったとしたら、今ごろ当然のように実家のお墓に納まっていたでしょうに。「あんな狭いところに押し込めたら、化けて出るぞ」というのが最晩年の言葉でした。十五になってたったのふた月で迎えた敗戦は、彼にとっての「コペルニクス的転回」であったに違いありません。多くの国民が「立場」上、戦争に駆り出され、最愛の夫や息子を亡くした妻や母が「立場」上、お国のお役に立ったと、にっこりすることを余儀なくされたあの戦争の理不尽は、いまも当時と変わらず受け継がれています。父が意識していたかどうかは知りませんが、そうしたものに抗う生き方を選び続けてきたのは確かかと思うのです。