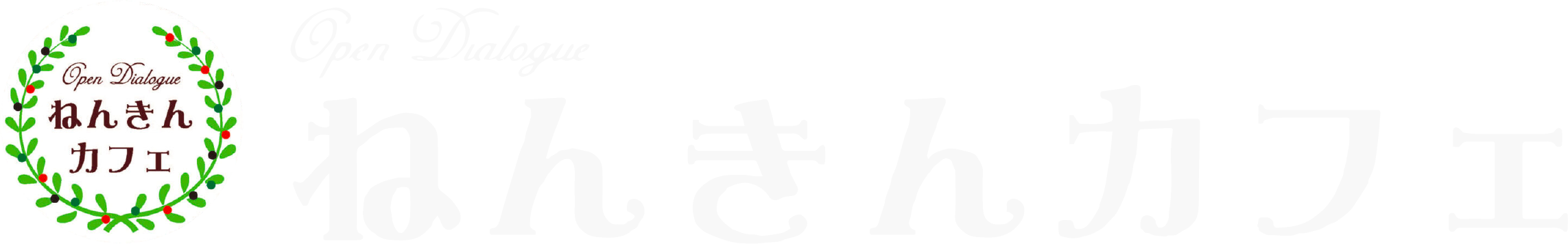普仏戦争に負けたフランスのアルザス地方は、当時のプロイセン領とされてしまい、学校でドイツ語以外は教えてはいけないことになりました。 1873年にフランスで出版された短編小説「最後の授業」の一節である「ある民族が奴隷となっても、その国語を保っている限り、牢獄の鍵を握っているようなものなのです」とは、フランス語で語られた最後の授業のくだりです。母国語は、生きる上で欠かせないものですが、それは人間にとってアイデンティティそのものだと思うのです。
新疆ウイグル自治区やチベット自治区に引き続き、中国北部の内モンゴル自治区で、今、言葉が絶滅の危機に瀕しているといいます。これは、かつて日本がやったのと同じ、「同化政策」で、 習近平政権は小中学校の授業で使用する言語をモンゴル語から標準中国語に変更しようとしています。それに対し、モンゴル族の人たちは大人も子どもも、政府系機関の職員までもが民族のアイデンティティを守るために立ち上がったとか。政府機関で、その職員が、堂々と民族の誇りをかけて抗議活動を行うことは、中国ではあり得ないことだといいます。
これらに共通する課題を、今の日本人が抱えていると自覚する人が、この国にいったいどのくらいいるでしょう。小学校での英語教育や企業の英語公用語化などは、ただでさえ思考停止に陥りがちな日本人を、深い思考が ますますできない状態に追い込む入口に思えてなりません。インドには、たくさんの言語がありますが、植民地時代が長かったこともあり英語を話せるかどうかによって、同じ国民同士が分断され、仲間だと思わなくなった歴史があります。母国語を疎かにして、深い思考を手放すということは、牢獄の鍵を失うばかりか、自ら進んで牢獄に入る行為ではないでしょうか。