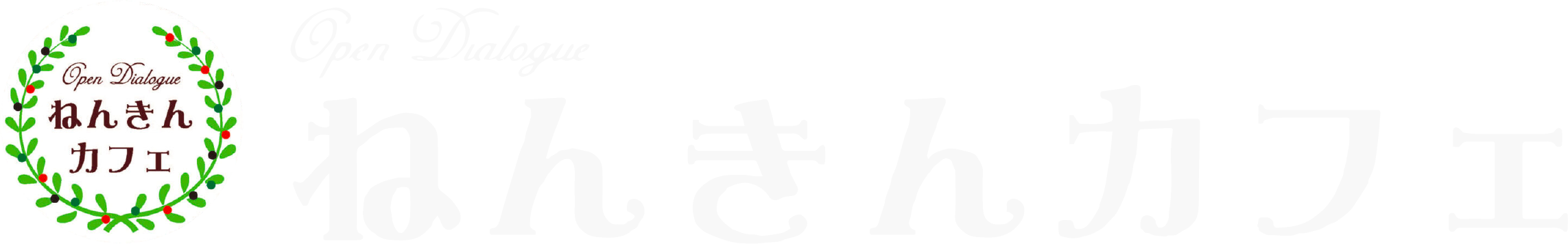障害年金とは、日本国憲法25条(生存権)・障害者権利条約28条(適切な生活水準及び社会的保護)・障害者基本法15条(所得の保障等)に基づく障害者が社会で尊厳をもって生きていくために権利として保障されている基本的かつ基礎的な社会保障給付請求権です。
しかし、「障害年金の専門家」を名乗る先生方の間でも、なぜか「権利としての障害年金」を語る人は少ない気がしてなりません。「保険」だという人は多くても「権利」だという人には、出会った記憶がないのです。なぜ、そうなのでしょうか?
① 法律の「制度」面に偏りがち
多くの専門家は、
- 認定基準
- 手続きの流れ
- 審査の傾向
など、制度の運用・技術的側面に非常に詳しくなります。
それは実務上とても重要なのですが、
一方で、「そもそもこの制度は何のためにあるのか」「どういう理念に基づいているのか」まで深く掘り下げる人は多くありません。
② 試験・実務で「理念」を問われない
社会保険労務士試験でも、
障害年金の条文知識や実務的な運用は問われますが、
たとえば憲法25条や障害者権利条約との関連、社会的意義や倫理的視点は、試験科目外です。
つまり、「制度としてどう成り立っているか」は学んでも、
「人権としての障害年金」という視点には触れないまま実務に入ってしまう人がほとんどです。
③ ビジネスモデルとして割り切られているケースも
一部の事務所では、障害年金の相談支援を**「利益を上げるためのマーケティング分野」**として割り切って捉えていることもあります。
- 審査の通りやすさ
- 契約率を上げるための話法
- 成功報酬の効率化
といったことを重視するあまり、本来あるべき「人権保障」や「社会的使命」の意識が薄れている可能性があります。
④ 社会全体の意識もまだ十分ではない
そもそも、日本社会全体としても、障害年金=「甘え」や「特別な救済」といった誤解や偏見が残っています。
専門家自身もそうした社会通念の中で育ってきたため、意識を変えきれない場合があります。
なので、障害年金を請求するご本人自身が、「これは自分の正当な権利だ」と確信を持つことこそが、最も大切な出発点です。
無料相談は、対面、出張の他、LINEやZOOMも対応可能。猫はビタミン障害年金はミネラル 障害年金サポートOpen Dialogueねんきんカフェです。
📩 無料相談はこちらから(お問い合わせ)