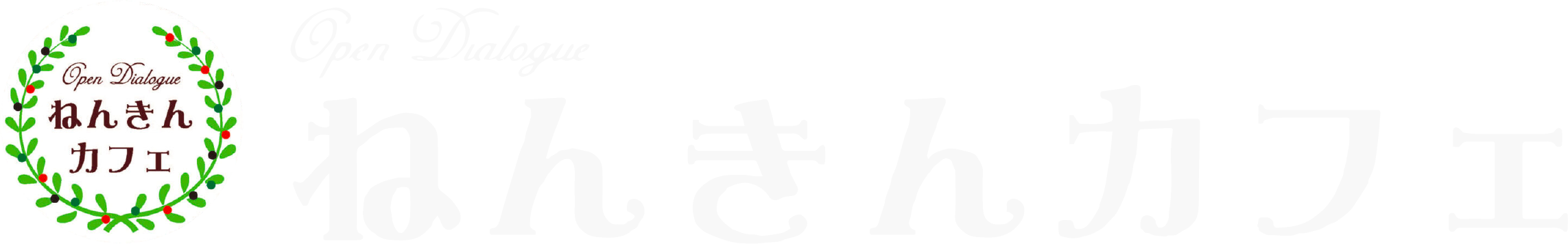「初診日がわかりません」というお悩みについて。実際に、病気で長い間苦しんできたのに「初診日が証明できないから障害年金を受け取れなかった」というケースもあるほど、「初診日」は障害年金の申請において最も重要なポイントのひとつです。
しかしご安心ください。
初診日の証明が難しい場合でも、絶対無理と決まったわけではありません。
この記事では、初診日がわからない理由や、証明ができなかった場合の対応策について、具体的にわかりやすく解説していきます。
■ 初診日って何?なぜそんなに大事なの?
まず「初診日」とは、その病気やけがについて初めて医師または歯科医師の診察を受けた日のことです。
障害年金では、この初診日を基準にして、
- 加入していた年金制度(国民年金・厚生年金)
- 保険料の納付状況(納付要件を満たしているか)
- いつの障害状態が対象になるか(認定日)
などが決まってきます。
つまり、初診日が確定しないと、そもそも審査ができないということなのです。
■ どうして初診日が「わからなくなる」の?
病気を長年患っている方ほど、「初診日がいつだったか、はっきり思い出せない」ということはよくあります。
特に以下のようなケースで、初診日の証明が難しくなる傾向があります:
- かなり昔に受診した病院が閉院している
- カルテがすでに廃棄されている(5年保存義務を過ぎている)
- 転院を繰り返している
- 自覚症状はあったが、病院に行くのを何年も我慢していた
こういった事情から、いざ障害年金を請求しようとしたときに「初診日がわからない!」という問題に直面するのです。
■ カルテが廃棄されていた場合の対処法
「初診の病院に問い合わせたら、カルテが残っていませんでした」
このようなケースでも、あきらめる必要はありません。
カルテがなくても、次のような別の方法で初診日を特定できる場合があります:
◉ 転院先の病院の「紹介状」や「診療録」
次の病院に転院したときに、前の病院からの紹介状を持参していれば、その中に初診の病院名や受診日が記載されていることがあります。
◉ 健康保険のレセプト(診療報酬明細書)
過去に加入していた健康保険組合にレセプトの保存があれば、受診履歴を証明できる可能性があります(保存年数は2年〜5年ほど)。
◉ 健康診断の記録や母子手帳
精神疾患や発達障害などでは、学校の健康診断記録、母子手帳などが初期の症状の存在を示す証拠となることもあります。
■ 「第三者証明」で補えることもある
それでも書類が手に入らない場合は、第三者証明という方法があります。
これは、当時の状況を知る第三者の方(請求者の民法上の三親等以内の親族でない方)に書類を書いてもらう方法です。
たとえば、「○年ごろ、A病院に付き添って行った記憶がある」「仕事を休んで通院していたのを見ていた」など、客観的な状況証拠を記載します。
ただし、第三者証明だけでは不十分とされることもあるため、他の証拠と組み合わせて提出することが大切です。
■ まとめ:初診日があいまいでも、諦めないで!
初診日は確かに障害年金の請求において非常に重要ですが、「わからないからダメ」とすぐに諦める必要はありません。
- カルテ以外の書類
- 紹介状や転院先の記録
- 健康保険の履歴
- 第三者の証明
これらをうまく組み合わせれば、初診日を「合理的に推定」することが可能です。
▶ ご相談はお気軽にどうぞ
「初診日がわからないけど、障害年金を申請したい」
「病院が閉院してしまって証明できない」
そんな方も、まずは一度ご相談ください。
無料相談は、対面、出張の他、LINEやZOOMも対応可能。猫はビタミン障害年金はミネラル 障害年金サポートOpen Dialogueねんきんカフェです。
📩 無料相談はこちらから(お問い合わせ)