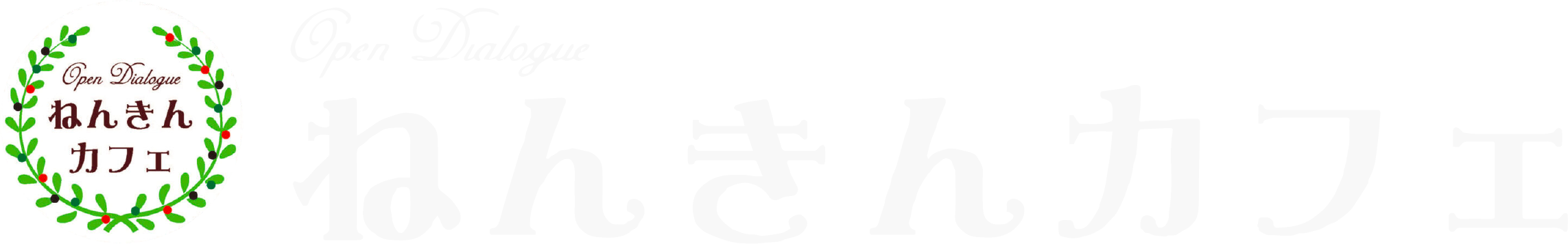目次
難病と障害年金の関係
障害年金制度では、「病名」そのものは受給要件ではありません。
大切なのは、病気によって生じている 障害の状態 や 日常生活の制限の程度 です。
つまり、どんな病名であっても、障害等級にあたるほど日常生活や仕事が難しい状態であれば、障害年金の対象になります。
難病に特有の困難
ただし、繊維筋痛症や慢性疲労症候群、化学物質過敏症、脳脊髄液減少症などの「いわゆる難病」には、障害年金の請求に特有の難しさがあります。
- 発病が緩やかで初診日の特定が難しい
症状がだんだんと出てくるため、「最初に病院にかかった日」がいつかが分かりにくい。 - 症状が多岐にわたる
全身の痛み、疲労感、集中力低下など、複数の症状が重なり合い、従来の診断書の枠に当てはめにくい。 - 専門医が少ない
診断や治療に詳しい医師が限られており、診断までに時間がかかる。 - 日常生活の制限が数字で示しにくい
「歩けるか・食事ができるか」といった機能障害で表せないことも多い。
認定に必要な工夫
そのため、難病による障害年金請求では、次のような準備が欠かせません。
- 病気の診断基準や治療方針について事前に調べておく
- 本人や家族から詳しく症状・生活の様子を聞き取り、整理する
- 医師とよく相談し、適切な診断書を書いてもらう
- 症状が多岐にわたる場合は、どの診断書の様式を選ぶか、必要なら複数作成してもらう
まとめ
難病は原因や治療方法が確立していないものが多く、その分、障害年金の認定も難しくなりがちです。
繊維筋痛症のように初診日が不明確で、症状が複雑な病気では、医師や専門家と連携しながら、日常生活の実情を丁寧に示すことが重要です。
障害年金は「病名」ではなく「生活への影響」で判断される制度です。
「請求できるのかな…?」と迷ったら、まずは相談してみてください。
無料相談は、対面、出張の他、LINEやZOOMも対応可能。猫はビタミン障害年金はミネラル 障害年金サポートOpen Dialogueねんきんカフェです。
📩 無料相談はこちらから(お問い合わせ)