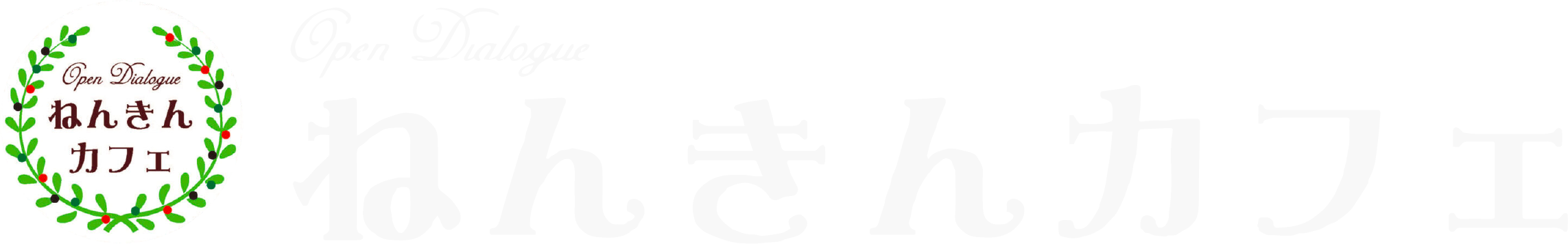「病気やケガにより療養中の会社員」という状況を例に、今回は傷病手当金から障害年金へ移行する際のロードマップを解説します。
厚生年金に加入している会社員の場合、傷病手当金(健康保険)と障害年金(公的年金)という2つの生活保障制度の連動がポイントとなります。
1. 🗓 障害年金申請の時系列ロードマップ
障害年金の手続きは、「初診日」を起点とした時系列で進行します。傷病手当金の受給期間(最長1年6か月)を、障害年金への移行準備期間として活用することが重要です。
| 時期 | 傷病手当金との関連 | 障害年金に向けた具体的な行動/ポイント |
| Day 1 | 療養開始 / 【初診日】 | 症状が出始め最初に病院を受診した日を確定させておきます。その証明となる「受診状況等証明書」が障害年金を請求する上で重要な書類となります。 |
| 〜1年3か月 | 傷病手当金受給中 | 療養に専念しつつ、日々の症状や日常生活での困難を記録(メモ、日記など)に残します。これは後の「病歴・就労状況等申立書」の土台となります。 |
| 1年3か月〜 | 障害認定日まで残り3か月 | 主治医に障害年金の申請意向を伝えると共に、初診日から1年6か月後の「障害認定日」が近づいていることを知らせます。診断書作成を依頼する準備を開始します。 |
| 1年6か月後 | **【障害認定日】**到来 | 障害認定日から3か月以内の日付を「現症日」とする診断書を作成してもらう必要があります。この時点の障害状態が1級・2級・3級のいずれかに該当するか審査されます。 |
| 1年6か月+α | 傷病手当金給付終了(または終了間際) | 年金請求書提出。診断書等の必要書類を揃え、年金事務所に提出し、**認定日請求(遡及請求)**を行います。 |
2. 📄 申請書類作成の2大ポイント
傷病手当金の「療養のための休業」という側面から、「障害認定日(多くは初診日から1年6か月経過日または症状固定日)以降の生活」を支える障害年金へ移行するには、「日常生活の制限度合い」を客観的に示すことが不可欠です。
(1) 診断書:主治医への正確な情報提供
特に重要なのが「現症時の日常生活活動能力及び労働能力」の欄です。
- 伝えるべきこと: 症状が重く、仕事に復帰できていない場合はもちろん、仮に短時間でも勤務を続けている場合、「通勤で付き添いが必要」「業務中に頻繁な休憩や配慮を受けている」「一般雇用者よりも業務量が大幅に少ない」など、職場や家族から受けている具体的な援助や配慮の内容を主治医に明確に伝えましょう。
(2) 病歴・就労状況等申立書:生活の実態を伝える
診断書で表現しきれない、日常生活における生々しい困難さを、請求者自身の言葉で伝えます。
- 日常生活の具体的記述:
- 「一人で買い物に行けない」「入浴時に見守りが必要」「金銭管理が困難」など、食事、入浴、金銭管理、対人交流といった各項目で誰の、どのような援助を受けているかを時系列で具体的に記述します。
- 就労状況の具体的記述:
- 「復職はしたが、業務内容は以前の1/3以下に軽減されている」「体調不良による欠勤・早退が月に〇回ある」「職場の特例子会社のような配慮を受けている」など、労働の制限を客観的に裏付ける事実を詳細に記載することが、障害等級の認定に大きく影響します。
無料相談は、対面、出張の他、LINEやZOOMも対応可能。猫はビタミン障害年金はミネラル 障害年金サポートOpen Dialogueねんきんカフェです。
📩 無料相談はこちらから(http://お問い合わせ)