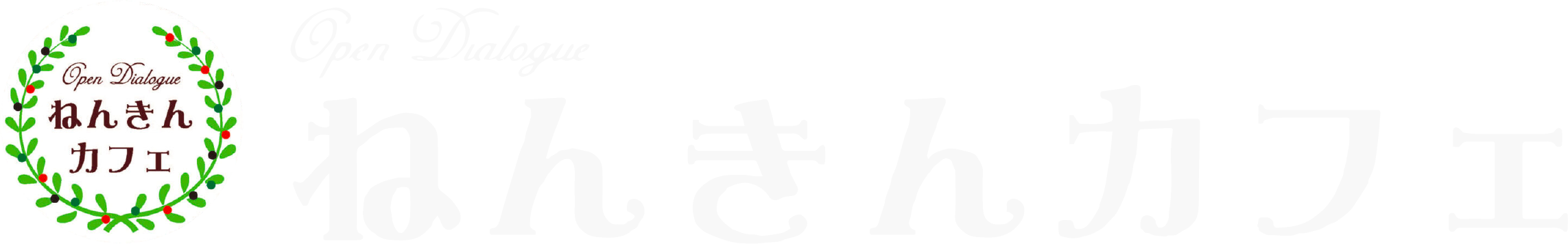― 生活の本当の大変さが、正しく届くために ―
知的障害のある方が障害年金を請求しようとするとき、
一番大切なのは 「本人の暮らしの実態が、そのまま診断書に反映されること」 です。
ところが、多くのご家族がこう話されます。
「本当は様々な援助が必要なのに、本人に“できる?”と聞くと“できる”と言ってしまうんです」
「働いているから等級は下がると思っていました…」
実は、どちらも心配しなくて大丈夫です。
障害年金は、“本当の生活能力” をていねいに見ていく制度です。
■1. 「日常生活能力」は“支援がない一人暮らし”を想定して評価されます
知的障害の認定で使われる診断書(精神の障害)は、
日常生活のどこで、どのくらい援助が必要か を細かく見ていきます。
ここで大事なのは、
🟩「できる」とは
助言や指導といった“特別な援助なし”でできること
という意味だということ。
たとえば、
- 料理は一人でできない
- お金の管理が難しい
- 服薬や身の回りの管理に声かけが必要
- 通院同行が必要
- 予定変更やトラブルがあるとパニックになる
こうした日常の“援助の量”が等級につながります。
そして、たとえ家族と住んでいて生活が安定していても、
もし一人暮らしだったらどうか?
という前提で評価されます。
だからこそ、家族や支援者の役割がとても大切になります。
■2. 就労していても、すぐに「軽い」とは判断されません
「働いているから、もう障害年金は難しいですよね?」
と不安そうに相談に来られる方も少なくありません。
でも、認定基準はこう考えます。
🟩“働いている”=“日常生活能力が高い”ではない
就労の評価では、
- 仕事内容
- 作業の難易度
- ペース配分
- ミスの頻度
- 周囲の声かけや見守り
- 配慮や援助の内容
- 人間関係のトラブルへの対処
など 働く場でどれだけ支援が必要か を丁寧に見ます。
特に、
- A型・B型
- 就労移行
- 障害者雇用での勤務
など「支援があって成り立っている就労」の場合は、
2級の可能性は十分残る とされています。
■3. 家族・支援者の“具体的な情報”が、等級を左右します
診断書を書くお医者さんは、普段の生活のすべてを見ているわけではありません。
だからこそ、家族・支援者の情報が欠かせません。
🟩診断書とセットで必要になる書類
「日常生活及び就労の状況」照会書
ここには、実際の生活を 具体的に、事実のまま 書くことが重要です。
たとえば、
- 朝の準備は一人でできるか?
- どんな声かけを、どれくらいの頻度でしているか?
- 料理・洗濯・掃除はどうしているか?
- お金の使い方はどんな様子か?
- 移動や通院は一人でできるか?
- 困った時に自分で判断できるか?
小さな困りごとも、実は大切な情報です。
🌟まとめ
知的障害の障害年金は、
本人の努力や「できる/できない」という口頭の回答ではなく、
生活そのものにどれだけ援助が必要かで決まります。
そしてその“本当の姿”は、本人が自分で説明することが難しい場合が多いため、
家族や支援者がていねいに、具体的に伝えることが不可欠です。
あなたのサポートが、
適正な等級につながる大きな力になります。
無料相談は、対面、出張の他、LINEやZOOMも対応可能。猫はビタミン障害年金はミネラル 障害年金サポートOpen Dialogueねんきんカフェです。
📩 無料相談はこちらから(http://お問い合わせ)