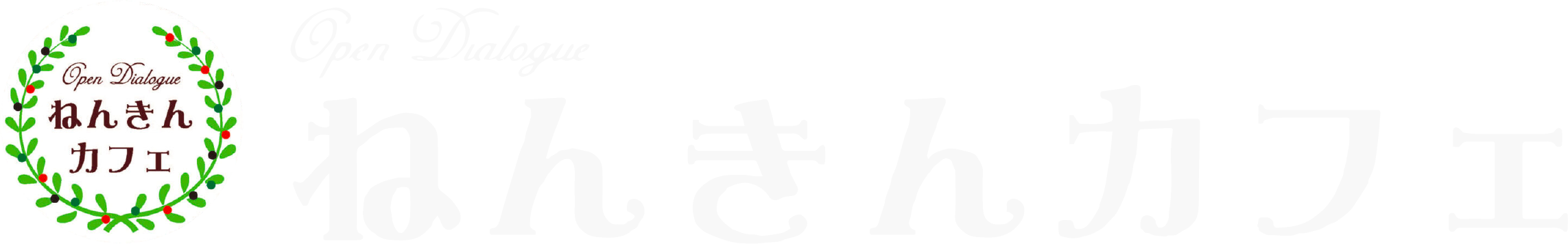障害年金の申請において、もっとも重要な書類のひとつが「診断書」です。
実はこの診断書、障害の程度が具体的に判断できるように8種類に分かれていることをご存じでしょうか?
間違った様式を使ってしまうと、書き直しや審査の遅れ、場合によっては不支給の原因になることも。
この記事では、診断書の正式な8種類とその対象について、わかりやすく解説します。
■ 障害年金の診断書は全部で8種類
厚生労働省が定める障害認定基準に基づき、診断書の様式は以下の8種類に分類されています。
| 様式番号 | 対象となる障害 |
|---|---|
| 様式第120号の1 | 眼の障害(視力・視野の障害) |
| 様式第120号の2 | 聴覚、鼻腔機能、平衡機能、そしゃく・嚥下機能、言語機能の障害 |
| 様式第120号の3 | 肢体の障害(手足の欠損や麻痺、人工関節など) |
| 様式第120号の4 | 精神の障害(うつ病、統合失調症、発達障害など) |
| 様式第120号の5 | 呼吸器の障害(肺気腫、COPD、間質性肺炎など) |
| 様式第120号の6-(1) | 循環器の障害(心臓病、不整脈、心筋症など) |
| 様式第120号の6-(2) | 腎疾患、肝疾患、糖尿病など(人工透析を含む) |
| 様式第120号の7 | 血液、造血器、その他の障害(膠原病、がんなど) |
■ なぜ8種類もあるの?
それぞれの障害には異なる評価基準があります。
たとえば、「視覚の障害」では視力や視野、「精神の障害」では日常生活能力、「肢体の障害」では関節可動域や筋力など、評価するポイントがまったく違うのです。
そのため、正しい様式を使わないと、必要な情報が記載されず、正しく審査されない恐れがあります。
■ 診断書の様式を間違えるとどうなる?
よくあるトラブルとして、誤った様式を選んでしまったというご相談があります。
実際に、次のようなケースがあります。
- 交通事故で「高次脳機能障害」を発症した場合、本来ならば「精神の障害用」を使用すべきところ「肢体の障害用」をもらってきてしまった。
- 「化学物質過敏症」で本来、「その他の障害用」を使用すべきところ「呼吸器の障害用」をわたされた。
このような場合、書き直しの依頼や、審査の遅れ、不支給のリスクが生じてしまいます。
■ どの様式を使うかはどう判断する?
基本的には、自分の症状が身体のどこの部分に現れているのかを正確に伝えることが重要です。
また、脳血管障害の後遺症など、複数の症状がある場合は、「肢体の障害用」と「言語機能の障害用」など複数の診断書を提出するケースもあります。
ただし、障害の程度が軽い場合は、複数提出しても等級には影響せず、診断書料が無駄になることもあります。
■ まとめ:診断書の様式選びも重要な戦略です
障害年金の申請は、「診断書の正しい様式を選ぶ」ことから始まっています。
この選択ひとつで、結果が大きく変わることもあります。
診断書の作成を依頼する前に、自分の障害に合った様式を確認し、主治医ともよく相談しましょう。
迷ったときは、どうぞお気軽にご相談ください。
無料相談は、対面、出張の他、LINEやZOOMも対応可能。猫はビタミン障害年金はミネラル 障害年金サポートOpen Dialogueねんきんカフェです。
📩 無料相談はこちらから(お問い合わせ)