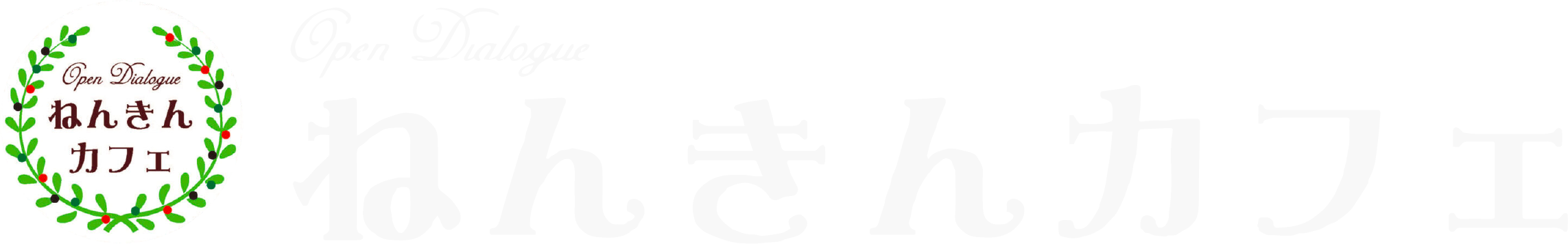こんにちは。障害年金専門社労士、横山です。
本日は、実際に私が関わった発達障害の若者2名の障害年金請求事例をご紹介します。
テーマは「さかのぼり請求(=遡及請求)」。つまり、過去にさかのぼって障害年金を受け取れる制度が、どんな条件で認められるのか、あるいは難しいのか――そのリアルな違いをお伝えします。
【事例①】医師と丁寧に連携して、さかのぼり請求が成功した女性(20代・24歳で請求)
この方は、小学生の頃に発達障害の兆しがあり、その頃から請求時点に至るまで同じ主治医の診察を受けていました。
請求時すでに24歳。障害年金を20歳時点までさかのぼって受け取れるよう、20歳当時と請求時点の2枚の診断書を準備することになりました。
ところが、当初、20歳時点の診断書は、日常生活の制限が軽く記載されており、障害年金の等級に該当しない内容だったのです。
しかし、ここであきらめず、当時の生活実態についてご本人やご家族、さらには支援員の方から丁寧にヒアリングを行い、医師にも詳細な情報を提供しました。その結果、主治医自身が当時の状況を思い出し「思い出させてくれてありがとう」と直接私にお電話をくださったのです。
実情に即した診断書により、20歳時点での状態が正式に評価され、無事にさかのぼり請求が認められた事例です。
【事例②】医師との意思疎通が難しく、さかのぼり請求が認められなかった男性(20代・25歳で請求)
もう一人は、発達障害のある20代の男性。請求時は25歳でした。
この方も幼少期から発達の偏りがあり、以前の主治医には長年診てもらっていました。しかし、20歳の頃には主治医が交代しており、新しい医師はそれまでの経緯を詳しく知らない方でした。
加えて、発達障害特有のコミュニケーションの困難さもあり、当時大学生だった本人から医師への説明がうまく伝わらず、実際の日常生活の困難さが反映されていない内容の診断書が出来上がってしまいました。
考えられる限りのサポート行ったものの医師側に情報が十分に伝わらないこと、記録の乏しさなどが壁となり、20歳時点の状態が障害等級に該当しないと判断され、さかのぼり請求は不支給(事後重症請求扱いとなり現在、障害年金受給中)となってしまいました。
【この2つの事例から学べること】
さかのぼり請求が認められるかどうかは、以下のような点が大きなカギとなります:
✅ 1. 主治医との信頼関係・継続性
長年同じ医師に診てもらっていると、生活状況を把握してもらいやすく、診断書にも反映されやすいです。
✅ 2. 情報提供の丁寧さ
診断書は医師の手で書かれますが、内容の元になるのは本人や家族の説明です。「正確な実情」が医師に伝わらなければ、正しい診断書にはなりません。
✅ 3. 記録と証拠の存在
カルテや学校の記録、家族のメモなど、「当時の様子」を示せる材料が多ければ多いほど、有利になります。
【まとめ】
発達障害は「見えにくい障害」です。特に若年期には「努力不足」「性格の問題」と誤解され、必要な支援が受けられないまま大人になる方も少なくありません。
障害年金を適切に受けるには、**「制度を知ること」「伝える工夫をすること」「医師との連携を大切にすること」**がとても重要です。
もし「うちの子もそうかも」「自分も対象になるのでは?」と感じた方は、どうぞお気軽にご相談ください。
一人ひとりのケースに合ったサポートを、丁寧にご一緒します。
無料相談は、対面、出張の他、LINEやZOOMも対応可能。猫はビタミン障害年金はミネラル 障害年金サポートOpen Dialogueねんきんカフェです。
📩 無料相談はこちらから(お問い合わせ)