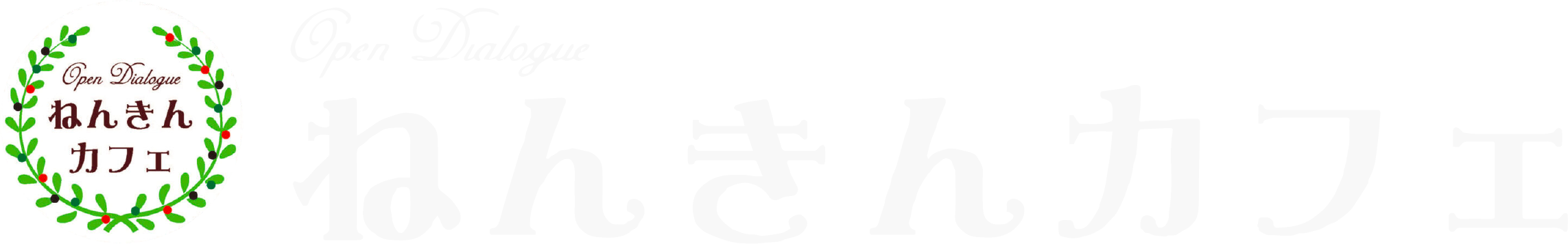目次
1. 現場でよくある「一刀両断」
実際の年金事務所では、障害年金に精通している担当者であっても、**「基準日に病院にかかっていなかったのなら、それはダメですね」**と即断されることが少なくありません。
これは職員が誤っているというより、マニュアル的な運用が強く根づいているためです。
担当者はどうしても「基準日=診断書必須=その日に通院していなければ不可能」と形式的に判断しがちなのです。
2. 判例が示した柔軟な考え方
しかし、東京地裁平成25年11月8日判決(判時2228号)は、こうした形式的な解釈を否定しました。
- 規則の趣旨は「客観的・公平な判断のための証拠確保」であり、
- 「基準日に受診していなかった」という形式理由だけで請求を排除すべきではない、
と明確に述べています。
この点は、実務現場での「即ダメ」という反応と大きく乖離している部分です。
3. 診断書の代替と補強資料
判決は次のような運用を認めました。
- 基準日時点に診療した医師の診断書がなくても、
- 後日の医師の診断書+当時の状態を裏づける客観的資料(カルテ、療育手帳、学校や施設の記録等)があれば、
- 規則上の「診断書提出」と同等に取り扱える。
特に知的障害の場合などには、時間が経過しても症状の基本的な性質が変化しにくいため、推認が可能とされています。
4. 実務での対応戦略
(1) 相談対応での説明
- 職員に「基準日に受診なし=不可能」と言われた相談者に対し、判例に基づく救済の可能性を伝えることが重要。
- 「難しいけれど、判例では柔軟に認められた例がある」と示すことで希望を持ってもらえる。
(2) 書類作成の工夫
- 「後日の診断書+補強資料」を体系的に整理し、「基準日時点を客観的に推認できる」と論理立てて提示する。
- 行政審査段階で否認されても、不服申立てや訴訟で戦える材料を残しておくことが大切。
(3) 疾患による見極め
- 知的障害・発達障害:基本特性が変化しにくく、判例の考え方を積極的に適用可能。
- 精神疾患・身体疾患:症状の変動が大きい場合は、より多角的な証拠(複数の資料、専門機関の記録)が必要。
5. まとめ
この判例は、年金事務所でありがちな「基準日に受診なし=即却下」という実務運用に対し、司法が「それだけで排除するのは不当」と明言した点で極めて重要です。
専門職としては、
- 相談者が現場で一蹴されて諦めてしまわないように、
- 判例を根拠に「補強資料による救済の道」を示し、
- 書類収集と論理整理を支援する、
という役割が求められます。
無料相談は、対面、出張の他、LINEやZOOMも対応可能。猫はビタミン障害年金はミネラル 障害年金サポートOpen Dialogueねんきんカフェです。
📩 無料相談はこちらから(お問い合わせ)