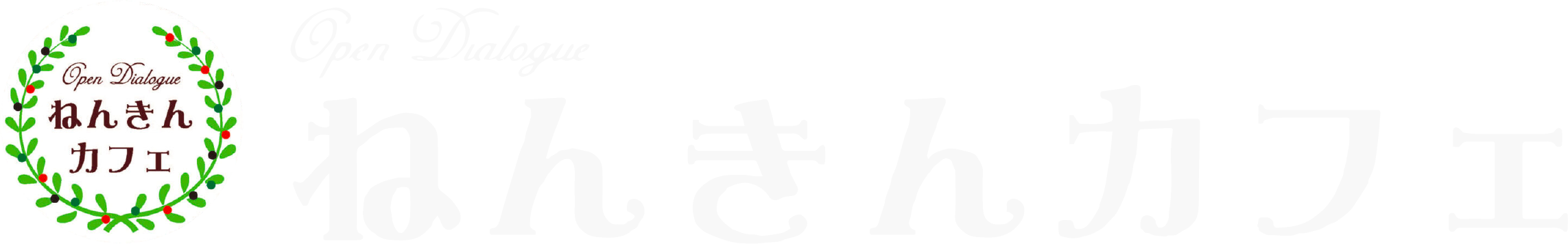脳脊髄液減少症とは?
脳脊髄液減少症は、交通事故や転倒などで頭を強く打ったあとに発症することがあります。
脳や脊髄を包む「硬膜」に穴が開き、そこから脳脊髄液が漏れ出してしまう病気といわれています。
この液体は脳を守るクッションの役割をしているため、減ってしまうと頭痛・めまい・耳鳴り・視力の不調・強い倦怠感など、多くの症状が出ます。
症状が続くと、日常生活や仕事に大きな影響を与えることになります。
障害年金と診断書の関係
障害年金を請求するには、必ず医師に診断書を書いてもらう必要があります。
この「どの診断書を使うか」が脳脊髄液減少症では特に重要です。
これまでの経緯
脳脊髄液減少症は、症状が多岐にわたり一つの診断書では表しきれないことがありました。
- 肢体の障害用の診断書(様式第120号の3)
→ 実際に多くの請求で使用され、認定された事例が多数あります。
(歩行の困難や手足の動かしにくさが中心になる場合はこちらが適しています) - その他の障害用の診断書(様式第120号の7など)
→ 2017年8月から、この様式も使えるようになりました。
(頭痛・めまい・倦怠感など、肢体以外の全身症状が目立つ場合はこちらが適しています)
現在のポイント
👉 「肢体の診断書」も「その他の診断書」も、どちらも使える
👉 症状の出方に応じて、主治医と相談しながらより適切な様式を選ぶことが大切
まとめ
脳脊髄液減少症で障害年金を請求する場合、診断書は一種類に固定されているわけではありません。
- 手足の麻痺や歩行困難が中心なら「肢体の障害用」
- 頭痛やめまい、倦怠感など全身の不調が中心なら「その他の障害用」
といった形で、症状の実態に合わせて診断書を使い分けることができるようになっています。
無料相談は、対面、出張の他、LINEやZOOMも対応可能。猫はビタミン障害年金はミネラル 障害年金サポートOpen Dialogueねんきんカフェです。
📩 無料相談はこちらから(お問い合わせ)