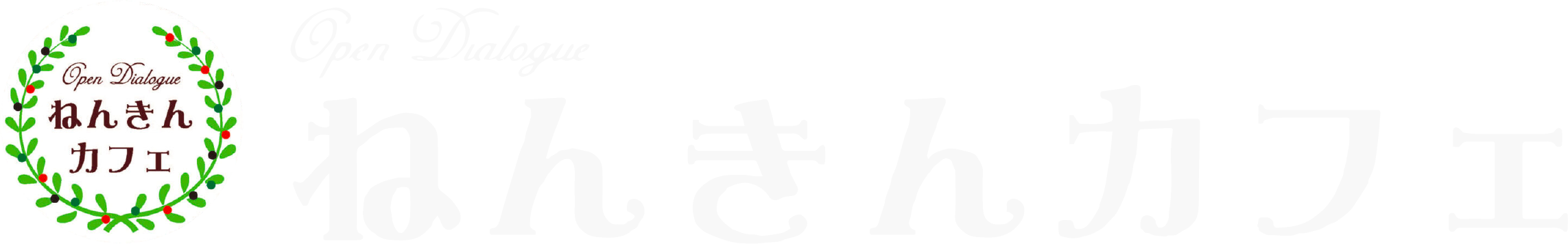障害年金は、「日常生活の不自由さ」と「働くことの困難さ」に応じて支給が決まる制度です。
でも、「てんかん」の場合、この制度の枠組みと実際の困難さの間にズレが生まれやすく、認定が難しくなることがあります。
てんかんと障害年金:制度の見方
認定制度では、てんかん発作の「重さ」「頻度」に加え、発作がない期間(間欠期)にどのくらい生活力や認知機能が低下しているかを見ます。 厚生労働省+2群馬障害年金相談センター |+2
ただし、診断書(精神の障害用)は、てんかんを前提とした評価項目ではなく、精神疾患や知的障害を想定した形式になっています。 年金ポータル+1
さらに、「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」からは、てんかんは除外された可能性があります。
なぜ認定がうまくいかないのか:ズレの本質
発作が起きていない時間帯は、普通に見えることが多い。
でも実際には、発作時の転倒リスク・意識障害・認知低下・薬の副作用などで、日常生活や仕事に制約がある。
そのズレが、「発作がない=障害軽度」と評価されてしまう原因になります。
どうすれば認定されやすくなるか?実践のヒント
- 発作データを具体的に記録する
回数・時間・状況・意識障害の有無などを主治医に伝える。 - 間欠期の症状も記載してもらう
疲労・眠気・集中低下・記憶力の減退なども、診断書に書いてもらうよう頼む。 - 補助資料を用意する
家族の記録・日常生活記録・職場記録などを添付して説得力を持たせる。 - 不支給なら審査請求を活用する
認定結果に不服があれば、再審査請求・審査請求のプロセスを使って争う。
最後に:制度を変える視点も大切
書類準備は重要ですが、それだけでは限界があります。
将来的には、てんかんを含む発作型疾患に合った認定枠を制度に組み込むことが不可欠です。
請求者・支援者・専門家が声を上げ、制度改善を求めていくことも同時に必要です。
無料相談は、対面、出張の他、LINEやZOOMも対応可能。猫はビタミン障害年金はミネラル 障害年金サポートOpen Dialogueねんきんカフェです。
📩 無料相談はこちらから(お問い合わせ)