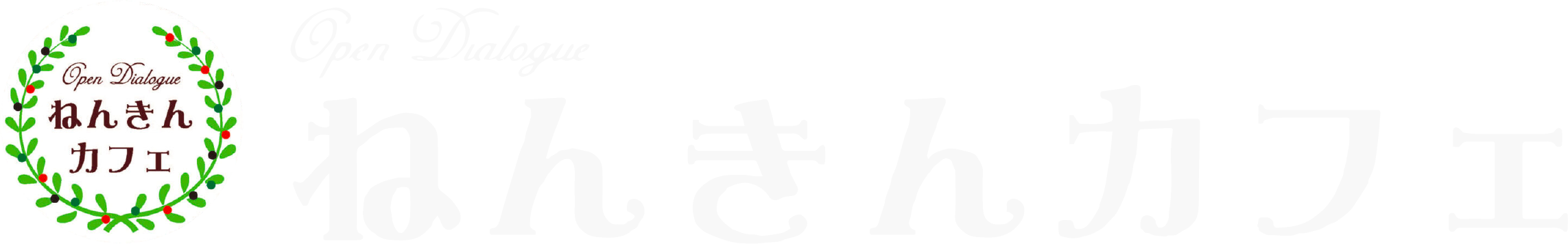統合失調症(Schizophrenia)は、妄想や幻覚といった「陽性症状」が最も知られており、これらが典型的な症状として広く認識されています。
しかし、障害年金制度においては、これらの妄想や幻覚がなくても、統合失調症と診断され、障害年金の対象となるケースは十分にあります。
本日は、障害年金の観点から、この点と、審査で最も重要視される**「生活への支障」**について詳しく解説します。
🔍 診断の鍵は「陽性症状」だけではない—残遺状態(陰性症状)の重要性
統合失調症の診断は、「妄想や幻覚があるか」の有無だけで決まるわけではありません。国際的な診断基準では、主に以下の3つのタイプの症状が一定期間継続していることが求められます。
| 症状の分類 | 主な特徴 |
| 陽性症状 | 妄想、幻覚、まとまりのない会話や行動など。 |
| 陰性症状 | 感情の平板化(無表情)、意欲の低下(自発性の欠如)、思考の貧困など。 |
| 認知機能障害 | 注意力、記憶力、計画を立てる能力(実行機能)の低下。 |
重要ポイント:
障害年金の審査基準である障害認定基準でも、統合失調症の障害の状態として「人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験」が例示されています。
しかし、妄想や幻覚といった陽性症状が目立たなくても、意欲の低下や感情の平板化といった陰性症状や認知機能障害が残り(これを残遺状態と呼びます)、それによって日常生活や社会生活に大きな支障をきたしている場合は、障害年金の対象となる可能性が極めて高いです。
💰 障害年金は「症状の有無」よりも「生活への支障」がすべて
障害年金の審査において最も重要視されるのは、特定の症状の有無ではなく、その病状によって日常生活や社会生活にどれだけ大きな制限を受けているかという点です。
精神の障害の認定は、診断書に記載された**「日常生活能力等の判定」に基づき、「社会的な適応性の程度」**を総合的に判断して行われます。
1. 日常生活能力の程度
- 家事ができない、金銭管理が困難、身の回りの清潔を保つことが難しいなど、生活能力が著しく損なわれている場合。
- 障害等級は、この「日常生活の用を弁ずることの不能度」や「日常生活の著しい制限」の程度が基本となります。
2. 就労や対人関係の困難さ(特に援助の必要性)
- 妄想がなくても、陰性症状による意欲の低下や集中力の欠如から、仕事の継続や他者との円滑なコミュニケーションが極めて困難である場合。
【特に重要:就労中の審査上の留意事項】
現に仕事に従事している場合であっても、その事実をもって直ちに日常生活能力が向上したとは捉えられません。
審査では、仕事の種類や内容だけでなく、職場で受けている援助(配慮)の内容、他の従業員との意思疎通の状況などが詳細に確認されます。
例えば、就労継続支援A型・B型などの福祉サービス、または障害者雇用を利用し、相当程度の援助や配慮のもとで働いている場合は、日常生活が著しい制限を受けている**(障害年金2級または3級の可能性)**と評価されることがあります。
📝 まとめ
統合失調症の障害年金認定は、幻覚や妄想といった陽性症状の有無で決まるのではなく、**陰性症状や認知機能障害による「日常生活の制限度合い」**で判断されます。
陽性症状が治まった残遺状態であっても、「生活を維持するためにどの程度の援助が必要か」を正確に伝え、適切に書類を作成することが、受給の鍵となります。
もし、ご自身の症状で障害年金の申請を検討されている場合は、専門の社労士にご相談されることをお勧めします。
無料相談は、対面、出張の他、LINEやZOOMも対応可能。猫はビタミン障害年金はミネラル 障害年金サポートOpen Dialogueねんきんカフェです。
📩 無料相談はこちらから(http://お問い合わせ)