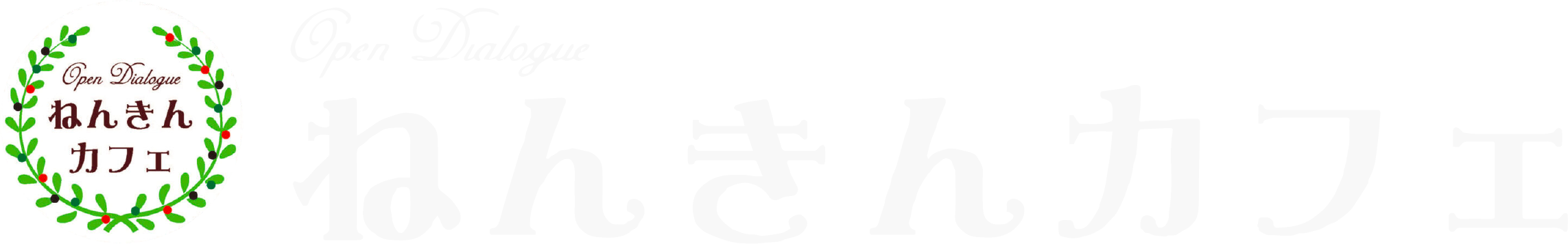「働いているから障害年金はもらえない」と思い込んでいませんか?実は、就労していても等級に影響のないケースと、等級判定において就労の状況が重要になるケースがあります。
障害年金は、原則として日常生活能力の制限や労働能力の制限に基づいて認定されます。この違いを理解することが、適切な申請への第一歩です。
1. 就労の影響をほとんど受けない傷病(客観的データが重視されるもの)
これらの傷病は、医学的な検査数値や手術の有無など、客観的なデータで等級が原則として決まるため、就労の有無が直接的に等級判定を覆す可能性は極めて低いです。
| 傷病・状態の例 | 判定のポイント |
| 人工透析(慢性腎不全) | 透析療法の実施自体が原則2級に該当。 |
| 人工関節・人工骨頭 | 挿入置換した事実が原則3級に該当。 |
| ペースメーカー・ICD | 装着した事実が原則3級に該当。 |
| 視覚障害・聴覚障害 | 視力、視野、聴力レベルなどの数値。 |
これらのケースでは、施術や治療法の開始日をもって認定日とすることが多く、等級は医学的事実によって定まります。
2. 就労状況が影響することがある傷病(日常生活能力・労働能力の制限が重視されるもの)
これらの傷病は、見た目の重症度だけでなく、日常生活や仕事にどれだけ支障が出ているかを総合的に評価して等級が認定されます。そのため、「働けている」という事実が、「日常生活に支障がない」と誤解されやすい傾向があります。
| 傷病・状態の例 | 判定のポイント |
| 精神疾患(うつ病、発達障害、統合失調症など) | 日常生活能力の程度や、仕事で受けている援助・配慮の内容。 |
| 内科疾患(心疾患、肝疾患、呼吸器疾患、糖尿病など) | 一般状態区分表に基づき、体調や活動性の制限の程度を総合評価。 |
💡 申請時の超重要ポイント
精神疾患や内科疾患の申請では、「働けている」という事実だけで判断されないよう、以下の点を診断書や申立書で具体的に伝えることが極めて重要です。
- 職場の配慮で、なんとか仕事を継続できている。
- 短時間勤務や仕事内容を限定してもらっている。
- 仕事以外の日常生活では、ほとんど動けない(身の回りのことも含め)。
- 他の従業員との意思疎通に困難があり、常に援助が必要。
「働いているからダメ」と諦めずに、どんな支障があるかを正しく、具体的に伝えることが、認定を得るための鍵となります。
まとめ
✅ 客観的データが基準の傷病(人工透析、人工関節など)は、就労の影響を受けにくい。
⚠️ 総合評価が基準の傷病(精神疾患、内科疾患など)は、就労の内容や支障の具体的な伝え方が結果を左右する。
「働いている」という事実と、「障害によって生活や労働が制限されている」という事実は両立します。ご自身の状況を正しく把握し、申請書類に反映させましょう。📝
無料相談は、対面、出張の他、LINEやZOOMも対応可能。猫はビタミン障害年金はミネラル 障害年金サポートOpen Dialogueねんきんカフェです。
📩 無料相談はこちらから(http://お問い合わせ)