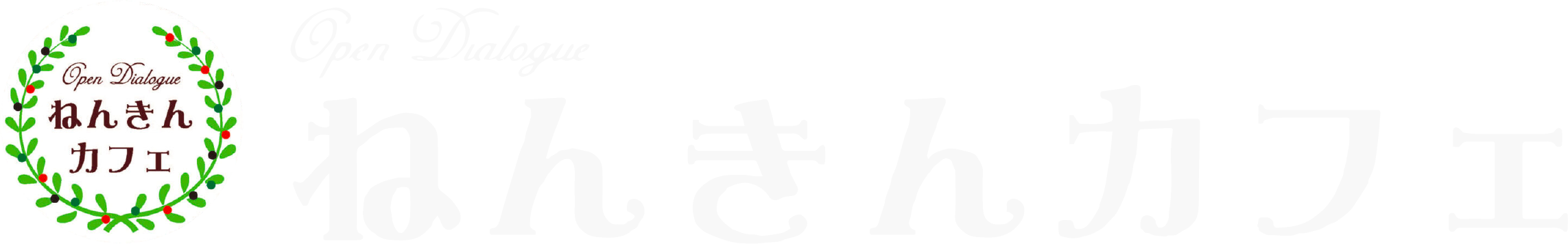「頭痛」や「てんかん」でも障害年金がもらえると聞いて、驚く方もいるかもしれません。
とはいえ、患者さんが多くいる割に実際にもらえる人は多くはありません。 それは、障害年金が**「生活への支障度」**を見る制度だからです。
🚨 受給を分けるシンプルなルール
障害年金を受給できるかどうかは、以下の基準をクリアできるかどうかにかかっています。
- 治療を頑張っても、病状が「改善しない」こと。
- その病気のために、「日常生活」や「仕事」が著しく制限されていること。
単なる「病気がある」という状態と、「年金をもらえる障害の状態」の間には、明確な境界線があるのです。
てんかんの場合の「ざっくり分かれ道」
てんかんが障害年金の対象になるかどうかは、主にこの2つで決まります。
1. 発作が薬で抑えられているか?
- 受給対象外の可能性が高い: 薬を飲んでいれば、発作がほとんど起きない状態。
- 理由: 治療で症状がコントロールできていると見なされるからです。
- 受給対象となる可能性が高い:十分な治療をしても、発作が続いている状態。
- 次の審査へ: この場合、発作の**「重さ」と「頻度」**で等級が決まります。
2. 発作の「重さ」と「頻度」は?(等級の目安)
| 等級 | ざっくりした発作のイメージ | ざっくりした生活への支障度 |
| 1級 | 毎月、重い発作(転倒など)がある | 常に誰かの援助が必要なレベル |
| 2級 | 年に数回、重い発作(転倒など)がある、または軽い発作が毎月ある | 仕事で収入を得るのが非常に困難なレベル |
| 3級 | 年に1〜2回程度の重い発作がある | 仕事に大きな制限が必要なレベル |
💡 最も重要なポイント:発作がない時も「困っているか」
発作の頻度が少なくても、てんかんに伴う記憶力や集中力の低下(認知障害)がひどく、簡単な家事や人とのコミュニケーションも難しいなど、日常生活能力が大きく損なわれている場合は、その総合的な支障度で2級などと認められることがあります。
頭痛の場合の「ざっくり分かれ道」
単なる「頭痛持ち」だけでは、障害年金の対象外です。頭痛が対象になる可能性があるのは、非常に限定的なケースです。
- 頭痛の原因: 頭痛自体ではなく、脳の病気など、原因となる別の疾患がある場合。
- 激痛による制限: 激しい片頭痛などにより、「痛み」そのもので日常生活や仕事が、上記のてんかんの基準(特に「仕事に大きな制限が必要」)に匹敵するほど支障がある場合。
**単なる「つらい頭痛」ではなく、「激痛や神経症状によって、まともに働いたり生活したりできない状態」**に達しているかどうかが、受給の境界線となります。
まとめ
障害年金の申請を検討する際は、**「病名」にこだわらず、医師に「治療を頑張っても、自分の生活や仕事にどれだけ大きな制限がかかっているか」**を正確に伝えて診断書を書いてもらうことが重要です。
無料相談は、対面、出張の他、LINEやZOOMも対応可能。猫はビタミン障害年金はミネラル 障害年金サポートOpen Dialogueねんきんカフェです。
📩 無料相談はこちらから(http://お問い合わせ)