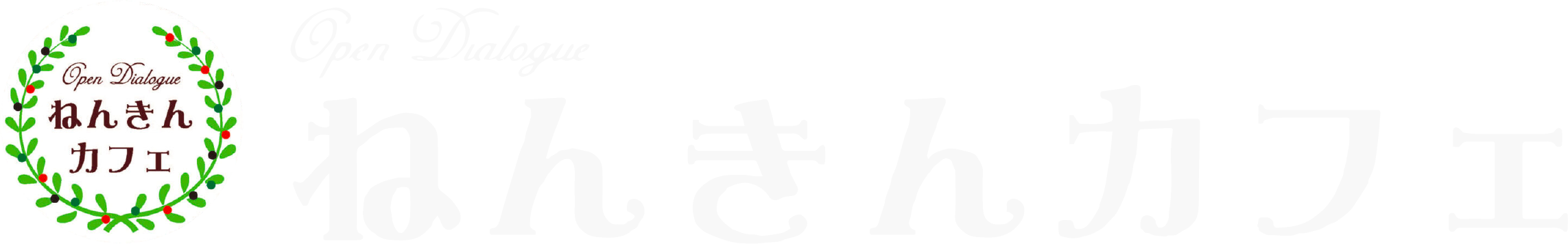私の父は寡黙な人でした。父に褒められた記憶があまり思い浮かばない私が、社会保険労務士試験に受かったとき、父は踊りださんばかりに喜んでくれました。父は望んでいたのです。社会保険労務士として私が地域のお役に立つことを。昨日はそんな父が亡くなってちょうど3年目の祥月命日。父の遺影に手をあわせながら、改めて人生の不思議に思いをいたす1日でした。
2017年の3月、私は長女の赴任先であるインドのバンガロールにいました。そこへ、父危篤の報せが届いたのです。取るものも取りあえず、タクシーに飛び乗り大渋滞の中、何とか空港に到着したものの私が乗るはずの飛行機の予約が、何らかの理由で取り消されていると空港のカウンターで聞かされた時には目の前が真っ暗になりました。
一緒に帰国できなかった長女をはじめ、名前も知らない数多くの人たちの助けを借りて、7000㎞の旅路の果てに私が父の枕元にたどり着いたのは、報せを受けた24時間後のことです。父はその後、まる3週間、最後の力を振り絞って6人いる子どもたちに、別れを惜しむ時間を与えてくれました。
あれから3年。夫とともに郷里に戻った私は今、父の遺した建物に立ち上げたOpen Dialogueねんきんカフェにいます。父亡き後のこの3年の到達点で待っていた「コロナ」は、私にとっても大きなマイルストーンで、この先は世界が一変するのかもしれませんが、ここからはじまる新たな文脈を死ぬまで、亡き父に見守られながら歩き続けるしかないと思っています。